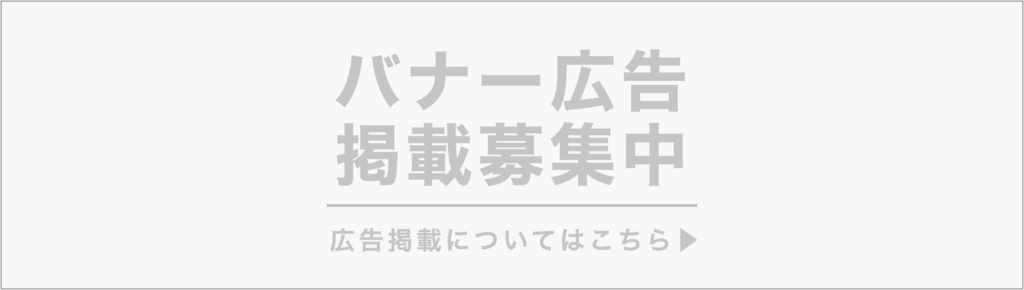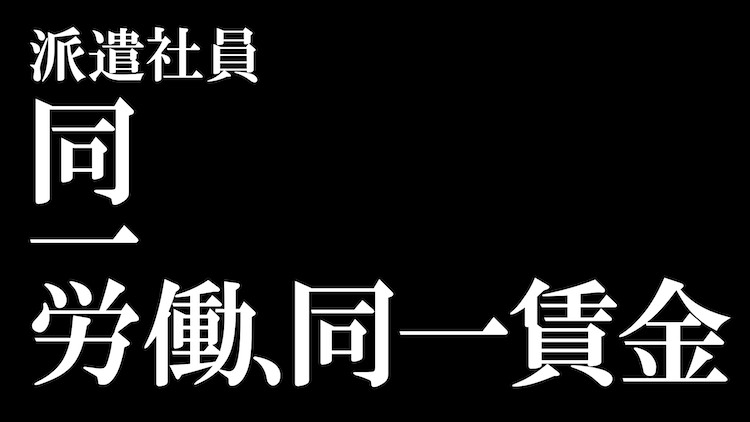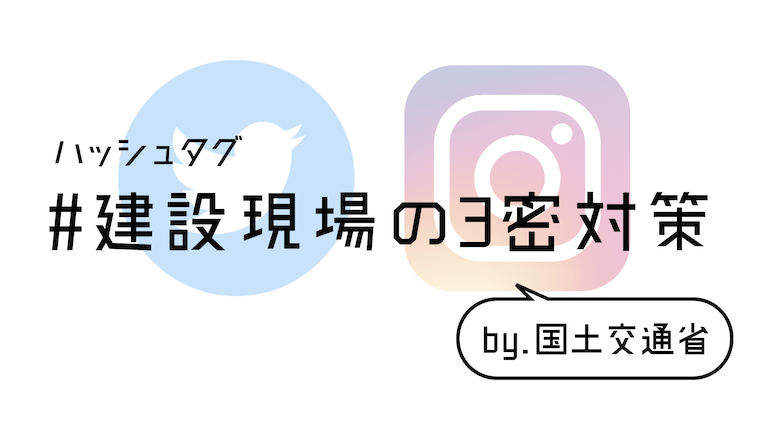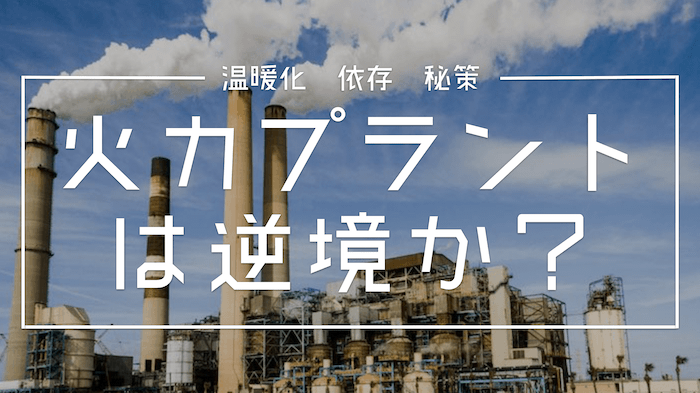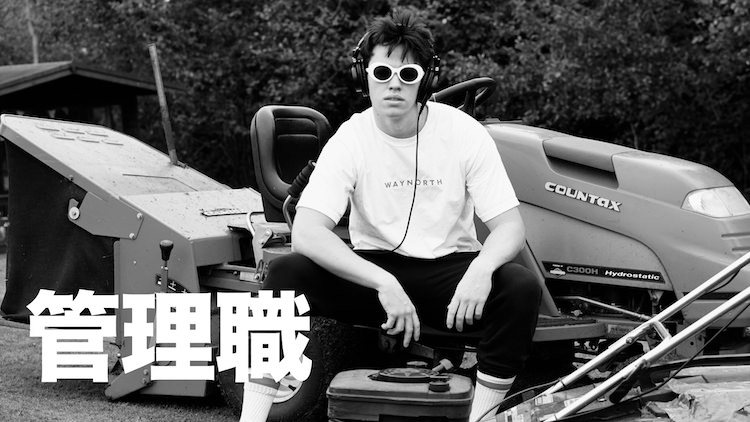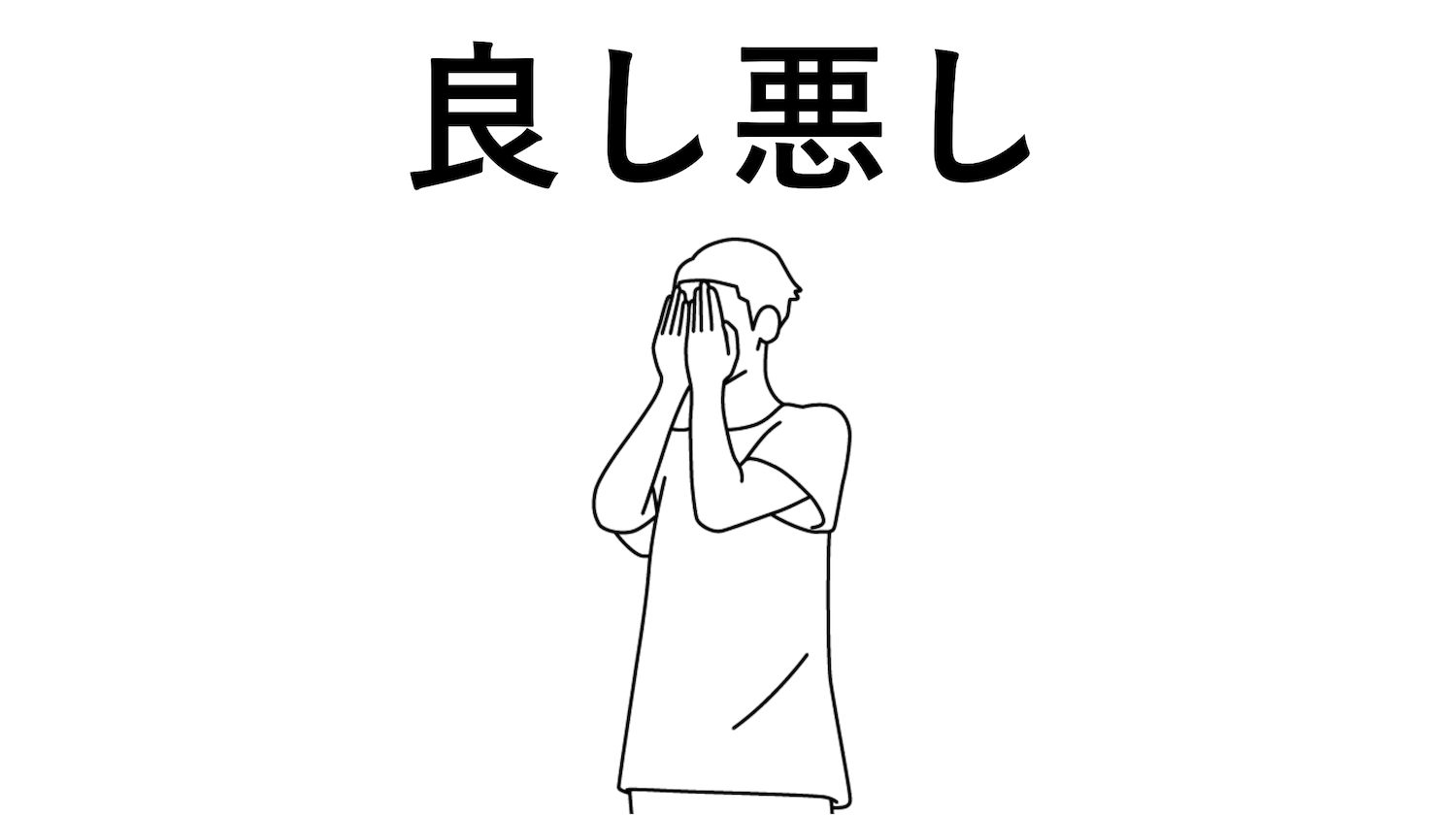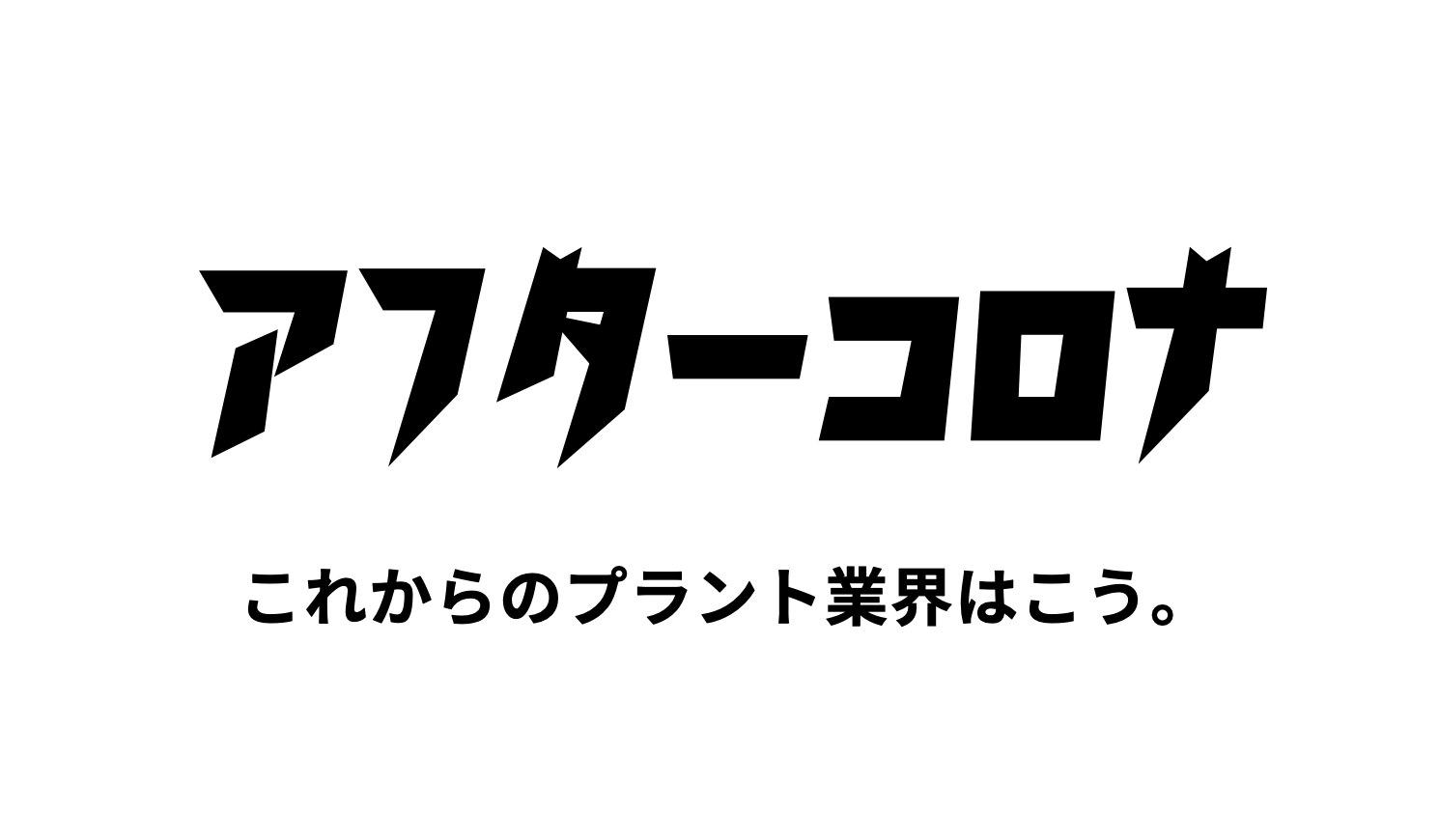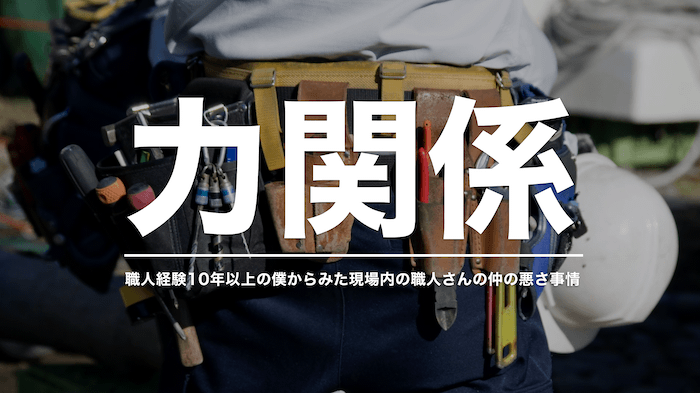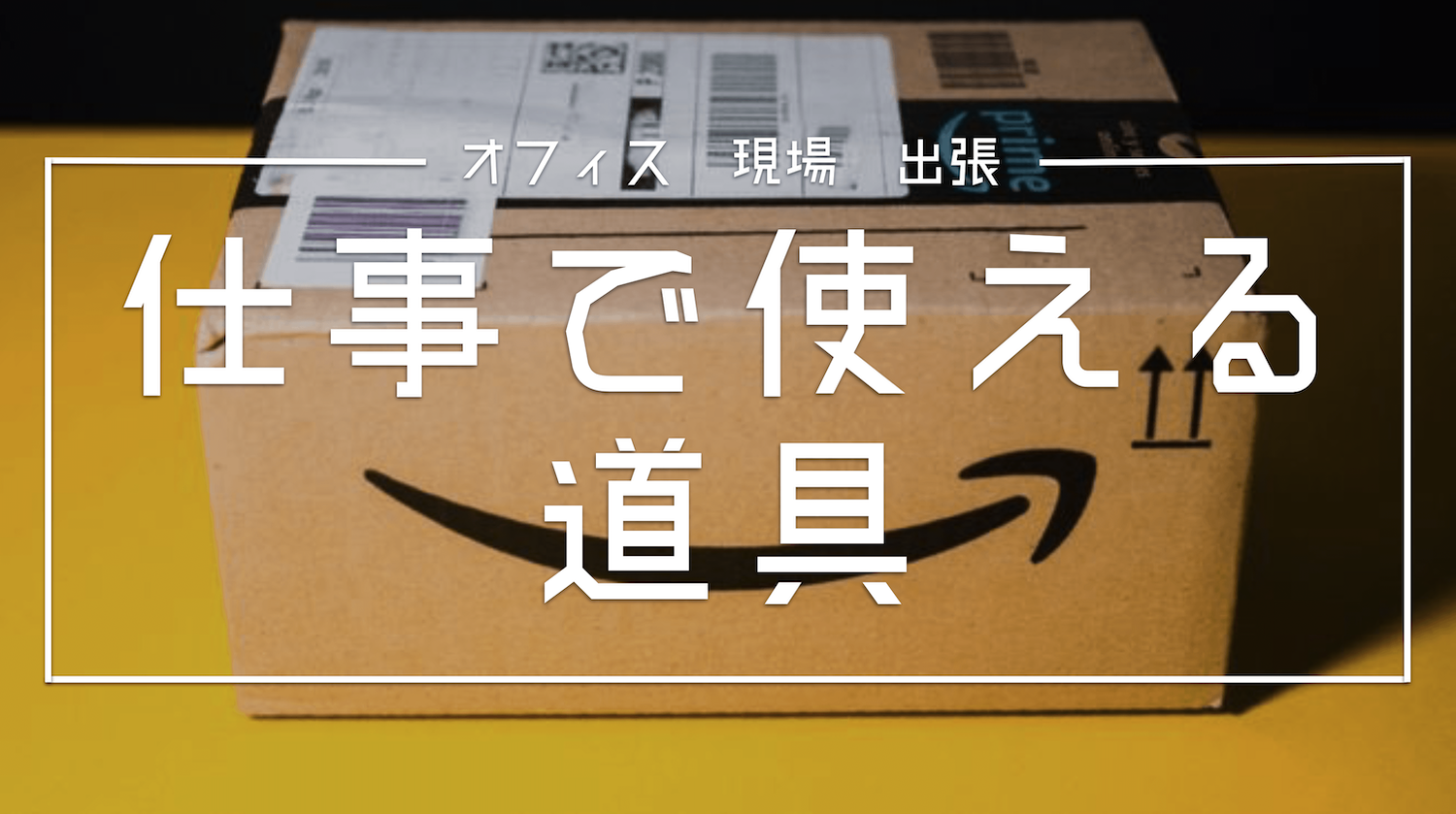優れた水素技術は真似る、成熟した水素戦略は盗む
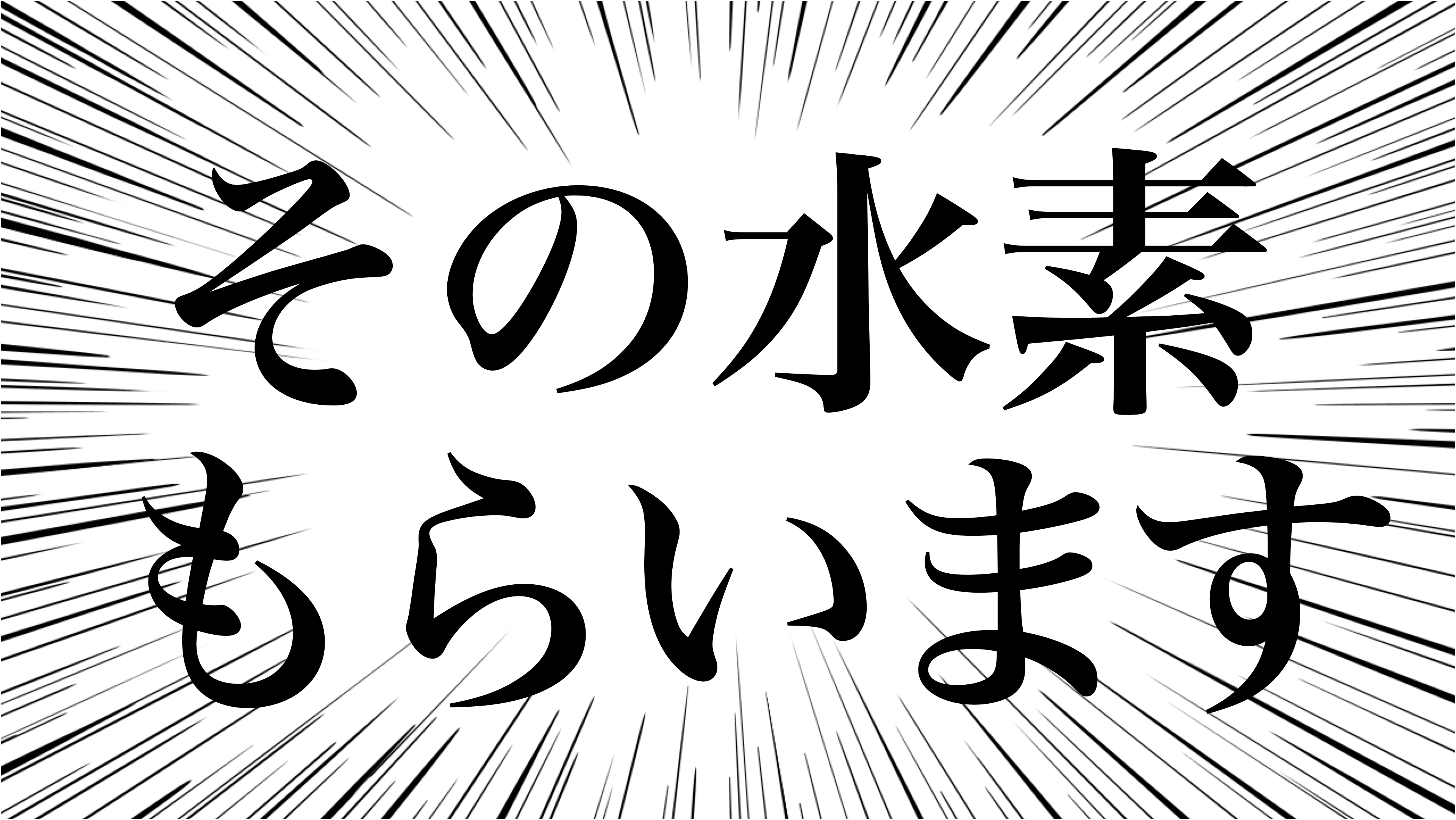
優れた水素技術は真似る、成熟した水素戦略は盗む

水素は勝ち馬か、なんなのか。
水素は脱炭素社会実現に向けた次世代エネルギーの大本命。
水素は水からも作ることができ、燃やしても二酸化炭素を出さないことから次世代エネルギーと注目されています。発電比率を水素4割にするとCO2は8割削減されるそうです。またエネルギー効率もよく、ガソリンの3倍とも言われています。
日本は世界から比べても割と早めに水素を使ったエネルギー開発について取り組んできましたが、じきに世界各国も注目しはじめ、今では激しい技術大競争となり、先頭を走ってきた日本も追い抜かれてしまう状況にあるみたいなんですよね。
これまで家電や自動車、スマホなどでもこのようなことは見てきました。この水素もまた同じ運命なのか。いや、この水素についてはまだ日の目すら見ていない。
今回はこれでまでの水素、これからの水素について見ていこうと思います。
水素の使いみち
水素事業については民間各社で独自に開発してきました。これに関する特許も早くからトヨタや日産も保有しています。私たちは早くから水素自動車の存在を知ってい「水素と言えば自動車」くらいのイメージも持っていたと思います。トヨタの量産型燃料電池自動車「MIRAI」です。
ちなみに8,600,000円です。
また、水素を燃料とする発電方法としては、原子力発電所1基分にあたる100万キロワットを目標にもするなど、経済産業省も国家戦略として後押ししてきました。
自動車や発電。今の現実社会では実用化というところまで来ていなく「期待」というレベル感。将来的には自動車から鉄道、船、飛行機、ロケットなどへと応用されていきます。一方、発電というカテゴリでは、家庭用レベルでの小規模エネルギー(家庭用燃料電池:エネファーム)といった身近なところまで近づいてきます。
なにより、水から作ることができるので停電時や災害時でも発電し、電気やお湯を供給することも可能。貯蔵することもできます。
背後に迫ってきた海外勢
勢いがあるのはドイツ。日本は2017年に国家水素戦略を制定しましたがドイツはその3年後、2020年でした。ドイツ政府による1兆円を超える多額の支援や補助金は勢いをつかせました。
水素製造装置を中東やアフリカに置き製造コストを減らし、現地で作られた水素を自国ドイツに輸入する戦略です。
また、オランダはもともと石油などの輸入港でもあるため、ヨーロッパ各国に水素エネルギーを供給する事を狙っています。
アメリカもおよそ1兆円の政府補助金で水素の製造、貯蔵、そして輸送を行う大規模な拠点を整備する予定だそう。
このように研究開発だけでなくその先のインフラ整備や実用化まで考えられていて、それを政府が手厚く支援しているのが特徴で、日本政府のさらなる資金支援や実用化、つまりは国として水素シェアを獲得しようという強い決断と支援がないとどんどん競争力を失ってしまうことでしょう。
Sponsored Links (by Amazon.jp)
水素の問題点
水素の効率的な輸送は液化です。
ただし水素の液化にはマイナス253℃という超低温が必要で、そのための設備投資が不可欠です。いくら低コストで製造できたとしても、輸送段階でコストがかかっては意味がない。これが日本が抱える問題です。
日本は島国。他の国とは遠いことが不利です。ヨーロッパのように隣接するようなところではパイプラインが使えますが、日本は船が必要になり、そのぶんコストが多くかかります。
川崎重工業は世界で唯一、液化した水素を運搬する船「ふろんてぃあ」を持っています。水素をマイナス253度に冷やし液化させ、体積を800分の1にする。このあたりはさすが日本といえるでしょう。
現在、水素の価格はハイオクガソリンと同値くらいと言われています。2030年には3分の1まで下げようとする方針ですが、ニーズとコストがバランス良くないと、そもそも水素社会が成立しません。
自動車分野では、水素自動車<電気自動車、の勢いも感じています。
ガソリンスタンドに変わる水素ステーションよりも、各家庭で補充できる電気のほうが普及は早いことは間違いなさそう。そして価格も安い。
| 燃費(1kmあたり) | |
| 水素自動車 | 約6〜7円 |
| 電気自動車 | 約3〜4円 |
| ガソリン車 | 約9円 |
1kmで比較すると数円の差ですが、同じ値段で東京から九州まで行けるか、それとも大阪までなのか、こういうことだと思います。
Sponsored Links (by Amazon.jp)
まとめ
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする目標を掲げています。
太陽光などの再生可能エネルギーだけで実現するのは難しく、とはいえ原子力発電は国民の反発もある。
だからこその水素です。
今、少しだけ技術でリードしている日本の水素技術をどう成長させるか。他国のように企業任せではなく国全体の規模で支えていかなければなりません。でもなければ他国で作られた水素を高いお金で買うことになるかもです。

日本の水素はまだ終わってない(と思う)